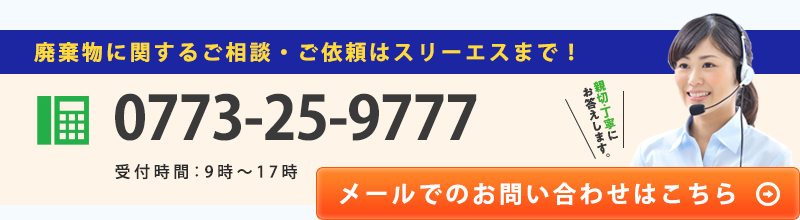氾濫ゴミの撤去方法に関する知恵とヒント
洪水関連廃棄物などの氾濫ゴミは通常の家庭ごみとは異なり、「災害廃棄物」として扱われ、特別な取り扱いが必要です。
氾濫ゴミすなわち災害廃棄物の撤去方法は以下のとおりです。
【安全確保と状況判断】
作業中は怪我をしないよう、安全な服装(長袖、長ズボン、手袋など)を着用してください。
被害状況の写真や動画を撮影してください。これは、後日、保険金請求や被災認定の際に必要となる場合があります。
●廃棄物の分別
災害廃棄物には、家具、家電製品、建築資材、土砂、流木など多岐にわたります。
地方自治体の指示に従い、可燃物、不燃物、粗大ごみ、土壌に分別してください。ガスボンベやフロン類を含む廃棄物などの危険物については、処分方法が指定されている場合があります。
土壌には泥や細かい破片が含まれているため、ふるい分けと分別が必要です。
濡れた木材は劣化しやすいため、破砕または焼却されることが多いです。
●仮収集・運搬
廃棄物は、地方自治体が指定する仮置き場または集積場へ運搬してください。土砂や瓦礫の除去には、下水管清掃車、強力な吸引車、高圧洗浄機などが効果的です。
汚泥の回収には、ビニール袋ではなく麻袋や竹袋の使用をお勧めします。ビニール袋は腐食しにくく、最終処分場で問題を引き起こす可能性があります。
●地方自治体への協力
災害廃棄物の処理は、原則として市町村の責任です。
市町村は、収集方法、処分場所、分別方法、収集時間、仮置き場所に関する情報を公表しますので、その指示に従ってください。
災害救助法が適用される場合、国が土砂・瓦礫の除去費用の一部を補助する場合があります。
●専門業者への依頼
大量の廃棄物、特殊な廃棄物、またはご自身での除去が困難な場合は、専門業者への依頼を検討してください。
建物の解体が必要な場合、解体によって発生した廃棄物は「産業廃棄物」として扱われ、専門業者によって適切に処分されなければなりません。
【災害廃棄物とは?災害時に発生する一般廃棄物】
災害廃棄物とは、自然災害によって発生した廃棄物のことです。特に日本は地震、台風、洪水などの災害に見舞われることが多く、自然災害の発生時期を予測することは困難です。
そのため、予期せぬ自然災害に備えて、災害廃棄物の処理方法を知っておくことが重要です。
災害廃棄物には、以下のものが含まれます。
・災害廃棄物
・避難所からの下水
・避難中に発生した廃棄物
災害廃棄物は、法律上は一般廃棄物として扱われ、市町村などの地方自治体が処理責任を負います。
災害廃棄物は、従来の一般廃棄物のイメージとは大きく異なり、産業廃棄物と誤解する人も多いようです。
しかし、廃棄物処理法では、産業廃棄物は「事業活動に伴って発生する廃棄物」と定義されています。つまり、災害は事業活動に伴って発生したものではないため、産業廃棄物ではなく一般廃棄物に該当します。
【災害廃棄物の5つの種類】
災害廃棄物は様々な物質が混ざり合った混合物であるため、処理前に分別する必要があります。分別は、不燃物や有害物質などの異物を除去し、処理に適した粒子径を均一にするために重要な工程です。
災害廃棄物は、分別前に以下の5つの種類に分類できます。
・木質系混合物
・コンクリート系混合物
・金属系混合物
・堆積物系混合物
・津波堆積物
それぞれの種類について個別に説明しましょう。
1. 木質系混合物
木質系混合物とは、主に木質系廃棄物からなる混合物の総称です。住宅などの木造建築物に使用された木質系廃棄物に限らず、生の木材や稲わらなどが含まれる場合もあります。
量は多いものの、識別や分別が容易なため、他の廃棄物との分別・回収が迅速に行われます。
リサイクル先に運搬するためには、埋め込まれた釘や金具などを取り除く必要があります。
2. コンクリート系混合物
コンクリート系混合物は、鉄筋コンクリート造建物の解体・倒壊により発生したコンクリート片や瓦礫を主成分とする混合廃棄物です。
この廃棄物を運搬する際には、可燃物や鉄筋を除去し、破砕する必要があります。
3. 金属系混合物
金属系混合物は、鉄筋、鉄骨、金属サッシなどの鉄鋼材料を主成分とする災害廃棄物です。また、家電製品や機械類を主成分とする廃棄物を指す場合もあります。
4. 堆積物系混合物
堆積物系混合物は、土砂崩れ、洪水、津波などの災害によって堆積した堆積物、砂、泥を主成分としています。その組成は、被災地の地形によって異なります。
5. 津波堆積物
津波堆積物とは、津波によって海底から巻き上げられ、陸上に堆積した堆積物です。
2011年3月に発生した東日本大震災により、化学物質や有害物質など、処理が困難な様々な物質が廃棄物に混入しました。そのため、津波堆積物に含まれる物質は、被災地の状況によって異なります。
【災害廃棄物処理の4つのステップ】
災害廃棄物の処理は、以下の手順で行われます。
・被災地からの廃棄物処理
・一次仮置場への搬送
・二次仮置場への搬送
・処理施設での廃棄物処理
被災地の復興のためには、災害廃棄物を迅速に処理する必要があります。それぞれのステップを見ていきましょう。
1. 被災地からの廃棄物処理
まず、被災地から廃棄物を収集し、搬出します。災害廃棄物を仮置場へ搬送する前に、被災地において可能な限り廃棄物の大まかな分別を行う必要があります。
大まかな分別を行うと同時に、人命救助や障害物の撤去のための道路の開通や救出経路の確保にも努める必要があります。
2. 一次仮置場への搬送
災害廃棄物は、仮置場において一時的に集積され、分別・保管・処理されます。一次仮置場は、被災現場から搬出された廃棄物を分別・保管する場所です。
一次仮置場は、災害廃棄物を迅速に搬出するために最も重要な場所です。
仮置場では、廃棄物の特性に応じて、以下のように分別・処理することが重要です。
・可燃性廃棄物
・不燃性廃棄物
・資源ごみ
廃棄物を適切に分別することは、コスト削減と最終処分量の削減につながります。
また、被災地では処理能力が低下したり、不足したりする場合が多いため、他の地域の施設を活用するなど、より幅広い視点で対応することが重要です。
3. 二次仮置場への輸送
二次仮置場は、一次仮置場から搬出された災害廃棄物を保管・選別する場所です。また、一次仮置場では処理できない破砕、精密選別、焼却などの中間処理も行います。
より精密な選別を行うために、二次仮置場には運動公園や工業用地など、ある程度の広さのスペースが必要です。
4. 処理施設での処理
二次仮置場で処理された災害廃棄物は、最終的に処理施設へ輸送され、そこで処理・リサイクルされます。
災害廃棄物の処理は、以下の手順で行われます。
・被災地からの廃棄物処理
・一次仮置場への搬送
・二次仮置場への搬送
・処理施設での廃棄物処理
【災害廃棄物の課題】
災害廃棄物の処理において、仮置き場の確保は大きな課題です。仮置き場の候補地として、以下のような場所が挙げられます。
・公園
・公民館
・スポーツ施設
・港湾等の公共用地
・廃棄物処理施設
しかし、上記のうち、二次災害の危険性が想定される場所や、地域の主要産業への影響が懸念される場所は、一般的に候補地から除外されます。
また、候補地への道路が被災したり、冠水したりする可能性があり、仮置き場の選定には時間と労力がかかります。その結果、災害廃棄物の搬出時に仮置き場の確保が困難になり、処理が遅延することがあります。
【災害廃棄物の円滑な処理のための対策】
災害廃棄物を円滑に処理するためには、事前の対策が重要です。具体的な対策は以下の通りです。
・仮置場の選定
・災害対策計画の策定
・国、都道府県、市町村、組合等の関係機関との協力関係の構築と協定締結
これらの対策を講じることで、災害発生時の災害廃棄物処理に関する初動対応が円滑に進みます。
また、地域住民に対し、緊急時の対応策に関する情報提供も重要です。情報を共有することで、災害発生時に関係者全員が協力して問題解決に取り組むことができます。
<まとめ>
最後に【まとめ|災害廃棄物の処理方法】
日本は自然災害の多い国であるため、災害発生時に発生する災害廃棄物の処理方法を把握しておくことが重要です。
災害発生時には人命救助が最優先ですが、廃棄物は周辺環境に悪影響を与え、火災の危険性も伴います。
災害廃棄物の除去には、仮置場の選定をはじめ、様々な準備が必要です。
大規模災害発生時においても、災害廃棄物の迅速な除去は復旧の迅速化につながります。
お問合せ
株式会社スリーエスでは、廃棄物収集運搬業を主体にビルメンテナンス、産業廃棄物中間処理、リサイクルなど「環境」をキーワードに事業展開し、地域環境と地域福祉に配慮し快適な空間作りや地域社会への貢献を目指しております。
関心やご相談のある方はぜひ弊社へお気軽にお問合せください。
※この記事に含まれる情報は公的機関の掲出物ではありません。お客様の責任でご利用ください。